<第13回>モスクワ音楽院大ホール
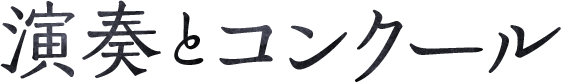
第7回チャイコフスキー・コンクールが行われたのは1982年6月10日からの一か月間でした。コンクールには、母が以前踊りのモスクワ公演の折に通訳をして頂いた、日ソ協会の山口さんを伴って同行しました。山口さんは母より一回りほど年長の女性で、モスクワ在住の彼女の友人たちに連絡を取って下さり、中でもカパルキナさんという、日本語の堪能な同年輩のご婦人がいろいろお世話下さったことを覚えています。
この方は音楽関係者ではないのですが、チェリストのロストロポーヴィチ氏と近所付き合いがあったとかで、ロストロポーヴィチがプロコフィエフのことを「彼は神様です」と語っていた話や、私が希望していたプロコフィエフの墓参りを実現してくれたりしたのでした。
ただ36年も前の話となると、記憶が抜けている部分も少なくなく、コンクールの出場日程がどうやって通知されたか、弾いたのが何日だったのかが思い出せません。参加者の数からして、一次予選だけでも10日間程度はあった筈で、私の出場順は期間の半ばくらいだったと思います。
出場に先立ち、ステージで演奏する楽器選びがあり、初めてモスクワ音楽院の大ホールに足を踏み入れた際は、さすがに感激しました。ステージにはチャイコフスキーの大きな肖像が国旗のように掲げられ、ホールの左右の壁にはアントン・ルビンシテインを含む、大音楽家たちの額が並びます。しかし、ニコライ・ルビンシテインの姿がありません。
不思議に思い、あちこち見回すと、ステージの枠の中央の頂点に北極星の如く、ニコライのレリーフが小さく据えられているのを見つけ、感無量でした。このロシア音楽の聖堂は当時を去る106年前、彼によって開かれたのです。
音楽院開設当初、チャイコフスキーはアントン・ルビンシテインが開いたペテルスブルクの音楽院を出たばかりの、一介の新米講師にすぎませんでした。学生時代、師のアントンと折り合いの悪かったチャイコフスキーは、ニコライに雇われなかったら、どうなっていたかわかりません。それが今や「チャイコフスキー記念音楽院」ですから、私からすると「『ニコライ・ルビンシテイン音楽院』だろうが。この恩知らずめ」と言いたくなります。
しかし、ロシア人のチャイコフスキーへの思いは格別のものがあるようで、「国民的英雄」というより、子どもが親を慕う感覚に近いものを感じます。恐らくポーランド人のショパン観は、故国を去った一天才への哀惜と賞讃であるのに対し、チャイコフスキーは母国の風土そのものの象徴とみられます。
ところで、私が選んだピアノはスタインウェイでしたが、並べて置いてあったベーゼンドルファーも素晴らしいコンディションで、音色が美しいだけでなく、鍵盤が指に吸いついて来るように馴染んで弾き易いのです。日本のローカルなホールの、年に何度も使わないようなピアノとは、同じブランドの楽器とは思えない程、その雲泥の差に驚きました、やはり数多の名手が連日弾きこなしてきた楽器の違い、そして空間の違いも大きいのでしょう。
出場を控えて、ホテルと音楽院での練習に行き来する数日間がありましたが、出番の二日程前だったか、人気の無い音楽院の階段の前を過ぎようとしたとき、不意に階段上から「中村さん」と私を呼ぶ声がしました。振り向くと中村紘子氏がいます。(つづく)(2018.11.15)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)
